 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
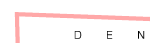 |
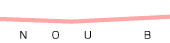 |
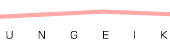 |
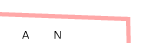 |
 |
 |
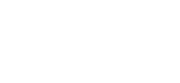 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
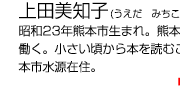 |
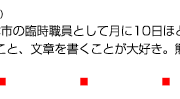 |
 |
 |
 |
 |
 |
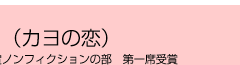 |
 |
 |
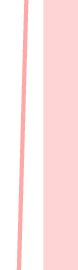 |
最盛期には遠賀川を石炭船が若松港をめざした。汽車と船で集められた石炭は若松から東京、大阪方面へ送られた。
石炭は朝鮮戦争を境に衰退をはじめ、深刻な不況におちいってしまった。
この室木線も昭和32年までは健在だった。
車は室木から頃末、室井、六反田と小さな炭坑のあった所を走っているのだが、炭坑の面影を残すものは何もない。ただの町の密集地と異なり、なだらかな山の手で、畑や田圃も広がっている。
「もうすぐ永谷ですからね。3年位前までは昔ながらの狭い道だったんですけど、今は道幅も広がり舗装もされています。全然違っていますよ。あっ、ここです。ここです」
広いコンクリートの道に立って、私はゆっくりとまわりを見渡した。畑があり、荒れ地があり、住宅がある。右手に石垣の塀があり、うっそうと木々が茂っている。神社だ。でも、建物は新しい。
西川炭鉱はどこかと問うと、右手の山手を指された。現在町営住宅になっている。
炭鉱住宅は軒の低いバラック住宅が6軒から8軒連なっていた。私が立っているこの地に建っていたのだろうか。トイレ、洗い場、風呂場は共同だ。
女達は大声でしゃべりあいながらっこで米を研ぎ、野菜を洗った。小さな洗い場はホッと一息いれる場所でもあったろう。
筑豊の女たちは、幼い頃から父や兄について坑内に下った。結婚してからは夫と共に。男以上に働いた女も多かったという。
炭坑の過酷な労働を支えたのは、物質的に貧しくとも信頼し助け合う人間関係があったからだ。
そのコミュニティーは、小さな洗い場からも生まれたと思う。まだ若くて未熟だったカヨは、この長屋の生活の中から多くのことを学んだ。
貧しさにもへこたれない、苦労も笑い飛ばし、たくさんの子供達を育てている女達に、明るさと強さを感じたかもしれない。
それぞれの家の土間にかまどか、煮炊きする場所があった。部屋の数は一間か、よくて二間。
その小さな空間で祖父母は愛し合い、夢を語り合った。いつかお金を貯めて折尾に出ていこう。小さな店を持ちたいと。ふたりは夢を実現させる為に精一杯働いた。
時には悦喜は人の2倍も働いた。2交替制の炭坑で睡眠を取らずに1日中働き続けたということだろう。
頑健な悦喜だからできたことだ。(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|
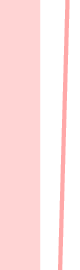 |
 |
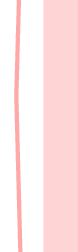 |
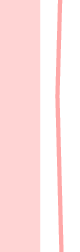 |
 |
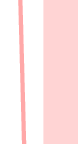 |
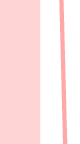 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
