 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
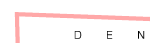 |
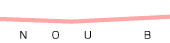 |
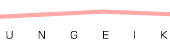 |
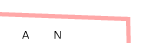 |
 |
 |
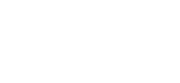 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
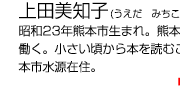 |
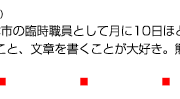 |
 |
 |
 |
 |
 |
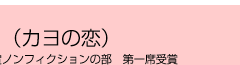 |
 |
 |
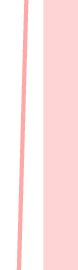 |
当時石炭は国の基幹産業である。遠賀川に沿って、西川、頃松、泉水、室井、水巻き、えびすと小さな炭鉱はたくさんあった。その炭鉱主達はこの「喜楽」で遊んだのではないだろうか。東京や都会から小説家やルポライターも炭鉱取材に来ており、折尾市の中心地に開店した「喜楽」を利用したかもしれない。また、官公庁に勤めるお役人を事業主が接客の場として使ったり、羽振りを利かせていた軍関係のお客さんも多かったはずだ。
小学校もろくに通えず働くだけだった悦喜の口からは決して聞くことはできなかった話。日本や世界の国々に政治や経済の話。政治家や戦争の話。なかには文学や人生論、哲学の話もあったろう。
たくさんの話の花が咲く部屋の中で、耳を澄ませ、心をときめかせて、黙って座っているだけで、カヨの心の中には新しい風が吹いたのだ。
カヨの人生は今までとは違った方向に大きく回り始めた。
女将としてなすべき当然の仕事として頭の中ではわかっていても、多感な年頃であった克巳には酔客に媚を売っているように思われて、許せなかったのかもしれない。
板長として、新鮮な素材を集めること、料理を工夫すること、「喜楽」の経営を軌道に乗せることだけを見ていた悦喜には、カヨの心模様は見えなかったが、大好きな母がよその男に心惹かれているのを、感受性の強い克巳は感じただろう。
そう思うと、私の心の中に克巳の悲しみや寂しさがストンと落ちてきた。
だから克巳はどまぐれたのだ。
中学校時代の友に野口雄一郎という九大教授がいた。熊本に来てから、克巳を訪ねてくる友人はほとんどいなかったので、二度も訪ねてくれたその人の名前を私も記憶している。
「九大の先生が……」と母は感激し、後日熊本の名物でも贈りましょうかと父に言ったが、余計なことはしなくていいと叱られた。克巳は意識的に、折尾時代の人間関係を断っていた。
その野口先生が、中学校時代はいつも克巳と1番を争うライバル同士だったと言った。しかし中学5年生になると克巳は突然に勉強をしなくなり、遊びまわったという。
野口先生は高等学校を経て、東京帝大を卒業し九大教授になった。当時の新聞に先生のエッセイや論文が載ったことがある。克巳はその記事を読みながら、「俺も真面目にやっていればな。今頃は……」とつぶやいたことがある。
私は言った。
「今さら悔やんでも仕方ないよ。それよりじいちゃん、ばあちゃんに感謝しなくては。お父さんの年で大学行けた人すくないんだよ」と。(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|
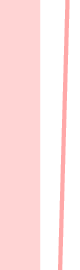 |
 |
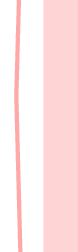 |
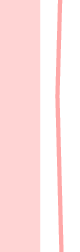 |
 |
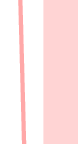 |
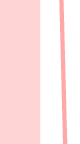 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
