 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
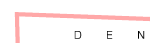 |
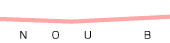 |
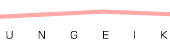 |
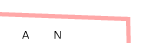 |
 |
 |
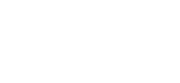 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
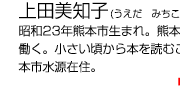 |
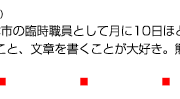 |
 |
 |
 |
 |
 |
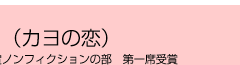 |
 |
 |
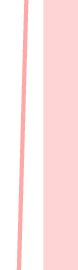 |
昭和18年になると戦争は日増しに激しくなり、店は傾き始めた。
克巳は当時のことは、「おやじの心がいちばんすさんでいる時。飲み、打つ、買うのどうしようもない生活が続いていた」としか言わない。
悦喜はすべての財産を賭けた勝負に負けたのだ。戦争という個人の力ではどうしようもない魔物に翻弄された。心の中に渦巻く荒波を静めるために、博打場に通い、浴びる程酒を飲み、女を抱いた。
それを必死で止めるカヨと喧嘩もし、心が離れていったのだろう。
そういう時、カヨの心を優しく抱き締めてくれた彼に出会ったのだと私は思う。
しかし夫は違った見方をした。取材旅行に出かける前日の夜、初めてふたりで祖母の恋の話をした時のことだ。
「ばあちゃんが43歳で家を出た時、おやじさん23歳だよな。そういう情況の中での母親の恋なら、もちろんいやだけれども、息子として男として解るって言うか、納得できる年だと思う。俺の勘だけどばあちゃんの恋はもっと早くから、おやじさんの10代後半だな。43歳の女性に会ってその人が辛い境遇にいるからってすぐに恋に墜ちてかけおちするか。ばあちゃんは30代後半。綺麗で魅力的だったはずだ。お互いに長い間好きだったからあの時代にばあちゃんはすべてを捨てて彼の胸の中に飛び込んでいけたんだよ」
「ちょっと待ってよ。だったらばあちゃんが先にじいちゃんを裏切ったことになる訳ね。ばかばかしい。ありえないよ。何言ってるのよ。知りもしないで……」
声を荒げてその話題は終わった。
しかし、今、この地に立って、目を閉じてカヨの女将としての姿を思っていたら、夫の言うこともそう違ってはいないとそんな気がした。
炭鉱で働いていた頃は半裸のまま地底の暗やみの中で、身体中ススで真っ黒になりながら働いた。魚屋時代も豆腐屋時代も朝早くから夜眠りにつくまで身体を使い働きどおしの毎日だった。
カヨは「喜楽」の女将になった。昼から風呂に入り、濃い化粧をし、美しい着物とそれに合う帯を締めてお客さんを迎える準備をする。一部屋一部屋に活けられた花。部屋やトイレ、庭の隅々にまで目配りをする。今夜のお客さんの名前を確認し、もてなしを考え、悦喜と料理の打ち合せをする。
大勢のお客さんを玄関で迎え、それぞれの部屋に女将として挨拶にも出る。
そこはどんな人達が集い、どんな会話がなされていたことだろう。(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|
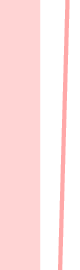 |
 |
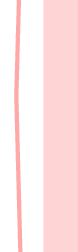 |
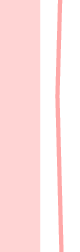 |
 |
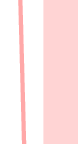 |
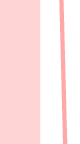 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
