 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
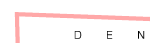 |
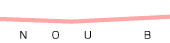 |
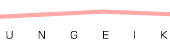 |
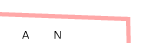 |
 |
 |
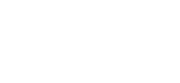 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
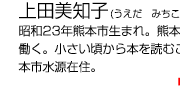 |
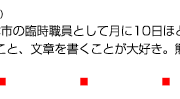 |
 |
 |
 |
 |
 |
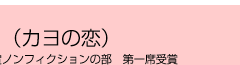 |
 |
 |
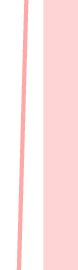 |
昭和62年3月28日、夜8時26分、亡くなるまでの8時間、祖母の最後の時間もあざやかに思い出せる。
風邪をこじらせ肺炎をおこしていたので死は時間の問題だった。腕から採られている血はどす黒く肺が全然機能していないのが私にも解っていた。
鼻からは酸素、腕には点滴注射、尿を出す管、身体の中にはいろいろな管が差し込まれていた。無意識のうちにそれらを取ろうとする祖母の手を私は何度も握り締めた。
しかし、もうその力もなくなった。
始めのうちは、母や私や子供達のことを気遣っていたが、今は父の姿だけを求めている。
「かっちゃん かっちゃん」何度も父の名を呼ぶ。私はかってこんな調子で呼ぶ声を聞いたことがない。今祖母は若い日に返り、幼い息子と向き合っているのだ。豆腐屋の仕事に追いまくられながらも、ひとり息子の子育てに夢中だった頃。
「かっちゃん、今晩のおかず何にしょう」
「かっちゃん、ごめん手がたらんと、この油揚げの配達を頼んでよかね」
「かっちゃん、今度のお休みの日、弁当作るけん、どこか遊びに行こうかね」
「かっちゃん」「かっちゃん」と明るい声で父を呼んでいる。
「苦しかろう、ばってんもう少し頑張らなんたい。いっしょに家に帰るけんな。家に帰ろうな」
父は堅いしわだらけの手を握り締めて泣いていた。
元気でいる時、祖母を見つめる父の目は愛憎の入り混じった複雑な色をしていた。
父は祖母の隣に座っていることが、息苦しいかのようにふっと席を立ってしまうことがあった。
母と3人で食卓を囲みながら黙っていちばんおいしいところを祖母の皿に取り分けていた。
毎日片足を引きずるように病院に通う祖母を後から見守っていた。
年を重ねてだんだん老いていく祖母がいとおしくてたまらないのに、心から包みこめなかった父。
でも今、ふたりは手を握りあい、なにもかも許しあっている。もう少し早くこんな時間が持てていたらどんなによかったろうと思いながら、ふたりの最後の時を見ていた。
息苦しさとの戦いが終わった。
あらゆる苦しみから解放された祖母の顔は柔らかで美しかった。
88歳で亡くなった祖母の葬式の日は小さな雨が降っていた。自宅での葬儀。庭先には近所の人達が傘をさして立っていた。父は集まった人達に深々と頭を下げると、話し始めた。
「今日は亡き母のために、お越し下さり本当にありがとうございました。近ごろの母は片足を引きずるような歩き方しかできませんでしたが、散歩や病院の途中に皆様方から声をかけられたり、助けられたりして感謝していました。不思議なことに、母が亡くなってから私の目に浮かぶのは、豆腐屋をしていた頃の若くて生き生きと働いていた母の姿ばかりです。当時の豆腐屋は夜中の2時、3時起きの辛い仕事でしたが、母はいつも笑顔でした。小学生だった私はよく豆腐や油揚げ売りを手伝わされました。友達が遊んでいるのに手伝いをさせられるのは嫌なこともありましたが、仕事を終えて帰ってきた私を、母はぬれた手を前掛けでふきふき強く抱き締めてくれました。その時の美しい母の顔が、今私の心にあふれているのです」(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|
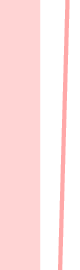 |
 |
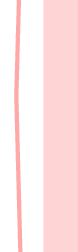 |
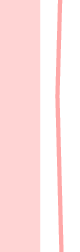 |
 |
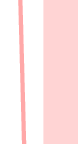 |
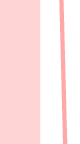 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
