 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
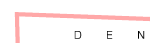 |
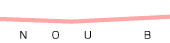 |
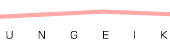 |
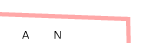 |
 |
 |
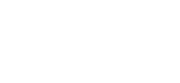 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
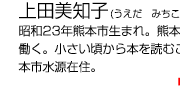 |
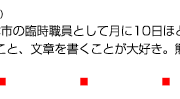 |
 |
 |
 |
 |
 |
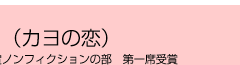 |
 |
 |
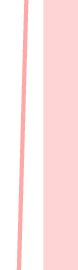 |
小学校しか行けなかった祖父母にとってひとり息子を大学に通わせることは生き甲斐のひとつだった。遊びまわっている息子を説得して地元の私立大学を受けさせた。克巳は不真面目な生徒だったが、1枚の卒業証書は熊本から再出発をした就職活動には役立った。
昭和21年、26歳の克巳は地方銀行の試験にパスして銀行員になった。
私は長い間、どまぐれの原因は時代にあると思っていた。昭和10年代、太平洋戦争が始まる前の重苦しい時代。若い純粋な学生が魔法のようにかかったマルクス主義への傾倒、共産主義、社会主義はもちろん自由主義者さえ警察に連行された時代。負ける確立の大きな大国アメリカ相手に戦争を始める予感。戦争反対を唱えることは命がけの行動だった。そんな時代が克巳から若者の夢や情熱を奪ったと。
確かにそれもある。が、カヨの恋もあるのだと確信した。
若い頃の克巳は昔話などしなかった。還暦を過ぎてから、酒を飲むと時々懐かしそうに思い出を語った。でも魚屋や豆腐屋時代のことだ。
昭和21年から17年までの5年間「喜楽」は全盛時代のはずなのに、克巳は一言も語らない。繊細な心をもつ思春期の息子は大切な母をとられたような嫉妬と寂しさに苦しんだ日々だった。
お互いに長い間惹かれあっていたからこそカヨは彼の胸の中にまっすぐに飛び込んでいった。彼は自分の家族を説得し、一年間一緒に住もうと小さな家を用意したのだという。カヨはその一年を一生分にしようと思った。
この恋を貫くことが、カヨの戦争だった。戦争にはいつも犠牲が伴う。夫や息子がどれほど自分を愛し必要としているか。自分の存在がどれほど彼の奥さんや子供さんたちの心を深く傷つけているか、はっきりと解っていた。
でも、カヨには心の炎を消すことはできなかった。
昭和18年、秋、カヨは籍を抜き風呂敷包みひとつ持って「喜楽」を出た。
昭和18年の日本は明日のない戦争へと進んでいた。世の中は不安に満ち、物資は乏しくなり静かな狂気が日本そ支配していた。1年後、いいえ明日のことさえ何も考えられなかった。
そんな時代の空気がカヨの恋を後押ししたのだ。
激しい喉の渇きを覚えたので私は歩きだした。駅前には喫茶店もあった。コーヒーでも飲んで少し休もう。時計を見ると4時少し前だ。4時間も歩きまわったのに疲れていない。興奮している。(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
|
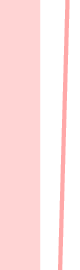 |
 |
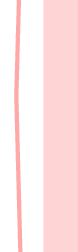 |
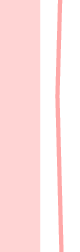 |
 |
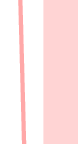 |
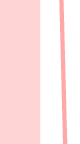 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
