 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
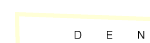 |
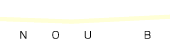 |
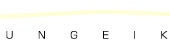 |
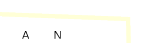 |
 |
 |
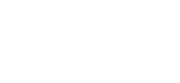 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
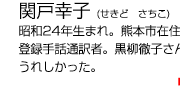 |
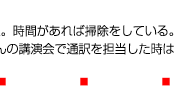 |
 |
 |
 |
 |
 |
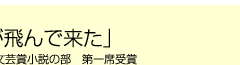 |
 |
 |
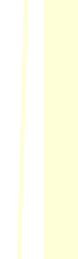 |
数日後、家具屋へ行った。
椅子は売れていなかった.買おうか、迷った。でも買わなかった。
また数日後家具屋へ行った。椅子はあった。チャンスかも知れないと思ったが、お金が足りない。内金だけ払って、後はどうにかしようとお目当ての椅子に座っていると、目の前に純ちゃんと呼ばれていた男性が立っていた。そして
「その椅子買うんですか」
と聞いた。
「えっ、ええ」
興奮してしまい、いつもと違う自分でも可笑しなくらい可愛い声になってしまった。
「そうですか」
沈んだ声だった。
「すみません。でも家に来ませんか、椅子に会いに」
「はっ」
相手の驚く顔は眼中に入れず、玉枝は家の電話番号を素早く書き、やや強引に書いた紙切れを渡した。
昨日離婚届けの用紙に署名捺印して夫へ郵送したばかりで、今日は晴れ晴れとして、天下無敵の日だった。後悔や恥ずかしさもなく、それより隅っこにでも行って、ガッツポーズをして、ささやかな勝利を祝いたい心境だった。 家に帰って母に椅子を買いたいから、お金を貸して欲しいと頼んだ。母は藤椅子を捨てるならお金を貸して上げてもいいと言った。でも、捨てたくなかった。あの藤椅子は好きだった。それは父が使っていたからで、それ以上の理由はなかった。
仕方がない、夫へ電話をしたが生憎通じなかった。
しかし次の日夫から電話があった。離婚届けの用紙は届いたけど、もう少し話をしたいと言った。そして同僚の奥さんが病院に入院しているので、代わりに見舞に行って欲しいと頼まれた。断わりたかったけれど椅子代が欲しかったので、また日当をもらう事を約束して承諾した。でも別れたい事は変わらないと告げた。プライドではない、プレゼントだった。
何日か過ぎて、夫と夫の両親が家に来た。その前に「伺います」と電話が掛かって来ていた。一度はきちんとした席を設けなければならないと、母とも話をしていたので「どうぞ」と答えて待っていた。
夫の両親が謝った。夫は黙っていた。それはふてぶてしいのではなく、新人の営業マンが最初の一言が言えないでいるような、もどかしい感じだった。
夫には兄と弟がいた。兄夫婦は子供は作らない主義で、仕事を楽しみに生きていた。弟はまだ独身で、ひとり暮しが性に合っていると常々口にしている人だった。
思った通り夫の両親は、孫の誕生を心待ちにしていた。
「一緒に暮さないと、その女性の方は言ってらっしゃるので、孫を抱くことは出来ないかも知れませんけど、この世のどこかに私達と血の繋がった命が生きていると思えばうれしいです。節句とか、誕生日とか、入園入学や卒業の時にはお祝いを送ろうと思っています」
窓から見える今日の青空のように、すっきりとした濁りのない本心を義母は口にしたのだろう。義父も頷いているから肯定を意味している。が、青空に少しばかり雲が浮かんだ状態に取れた。肝心の夫と言えば、義父より雲の量は多く、一雨来そうな気さえする。傘はもちろん持っているけど、差し掛ける事はもう出来なかった。
この部屋に集まった五人は、一つの新しい生命の誕生は喜ばしいと思いながらも、反面背中に鱗がくっ付いたようで、重かったり、チクチクしたりして座蒲団から腰を浮かす時、各自時間が掛かった。
玉枝は話し合いが何ら衝突する事もなく、淡々と、たまにはそれぞれがお茶を啜る中で進んで行けたのは自分にあると思った。愚痴や嫌味、くやしいとか悲しいとか一切小言を言わなかった。それをあなた達は知っているのですか。と誰も誉めてくれない事への怒りを込めて、部屋を出て行く四人の背中に無言で投げ掛けた。もちろん返事は返って来ない。ムカムカした腹立たしい思いは一層増して来た。そんな時母が今日は珍しく薄く口紅を差していて、その唇を耳元に近づけて
「新しい人生が待ってるね」
赤い唇らしく、祝いの言葉を囁いた。
お陰でムカムカした腹立たしい思いはまだ生まれ立てで、ふわふわしていて完全な姿を成していなかったので、時間を掛けずにさよならが言えた。
今日一日が終ろうとしている。夏の日の風鈴の音を聞くような清涼とした気持ちにはなれないけれど、今迄とこれからの間にバサッと鋏を入れた。これからの所に手を添えていたので、今迄の部分が下へ落ちた。これからの所は白く、白く光っていた。(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|
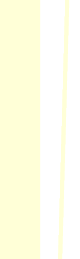 |
 |
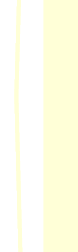 |
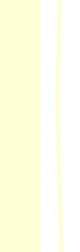 |
 |
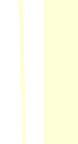 |
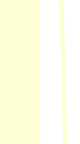 |
 |
 |
 |
 |
 |
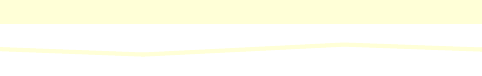 |
 |
