 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
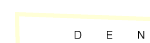 |
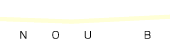 |
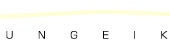 |
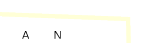 |
 |
 |
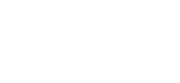 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
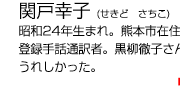 |
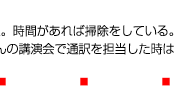 |
 |
 |
 |
 |
 |
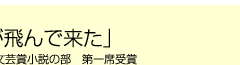 |
 |
 |
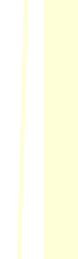 |
夫との生活は十年近くが経ち、子供はなく家事をこなしながら暮して来た。
どちらかと言えば夫からの要求はほぼ受け入れて来たつもりだった。夕食に「金眼鯛のこってりした煮付けが食べたい」と会社から電話が掛かって来れば「分かった」と答えた。朝食の時「今夜は白ではなく、クリーム色のシーツでいつもと違う、右左入れ替って寝てみようか」と夫が囁けば「ふふっ」と笑って頷いた。
「お喋りが好きになって欲しい」
お喋りが好きな夫からの注文には努力しようと思った。他にもある。ある、ある。別れて欲しいと言われた夜から月や星の力を借りても眠れず、ベッドに座ったまま口をぽかんと開けていた。朝が来て太陽の光を受けてもやっぱり眠れず、開いた目は嫌な所だけを見ていた。これでは目が汚れ、いずれは体中も汚染されてしまいそうで、この場から逃げた。
母もひとりで平穏に暮している訳ではなかった。数年前に父が亡くなってから、時々兄のお嫁さんが様子を見に来てくれるが、長い時間居ることはなかった。父が亡くなる時、父は母ではない女の人の名前を口にした。
「ユキさん」と。か細い声だったが臨終に立ち会った五人全員が聞いた。あの父が――。息を引き取っても悲しみの中に突然驚きがドカドカッと入り込んで来た。でも驚きは暴れる事もなく只隅っこでおとなしくしているだけだったから、バタバタと涙を落として泣いた。母はこんな時だから大っぴらに泣いてもいいのに、私達とは違った背中を向けシクシクと龍った涙の流し方だった。
時々来てくれる兄のお嫁さんも、父が口にした母意外の女性の名前を聞いた中のひとりだった。だから母はこの人に来て欲しくなかった。兄夫婦はうまくいっている。子供が三人いて、問題にぶつかり心を痛めているなんて聞いた事がなかった。
その点母は玉枝にやさしかった。
「男って嫌な生き物ね」と、よく話をして来る。
「そうね」と答えるたびに母の機嫌はいい。ここは間違いなく玉枝にとって、居心地の良い所だった。だから「ビール飲もう」「いや今夜はワインにしよう、赤ね」「いいねー」と意気投合する事も多く、たびたび軽い酒盛りを開き、乾杯をしては二人に付いた男運の悪さを退治した。
母は父の遺品を次々に捨てた。「あら、もったいない」と言っても「いいから、いいから」と、捨てる。でも仏壇に置いてある父の写真はしげしげと眺めながら「本当は捨てたいんだけど、あんまりいい顔をしているから捨てられず、腹が立って投げてしまうのよ」と言う。母の心の枠は甘くなっている。だから飛び出した心は、怒ったり、照れたりして落ち着きがなく、動いているのだろう。
父が作った縁台がある。詰めたら三人から四人は座れる。木々の葉っぱ達が重なり合った庭の隅に置いている。塀らしい囲いもしていないので近所の人や、そうでない人もそこを通ったついでに休憩したり、座ってお喋りをする。少しぐらいの雨ならそのままにしているが、ひどい雨の時は軒先に入れる。しかし入れるのをうっかり忘れたりすると、誰かが覆いを被せてくれている。もはやこの縁台は町内の人達の物と言ってもいい。だからこれは処分する事は出来なかった。
玉枝は二階の部屋を使っていた。ここには藤椅子がある。父が使っていた古い物だ。ひょっとしたら父は藤椅子を斜めに倒し、背中や腰をやんわりと当て、まずいい気持ちになって最後に口にしたユキさんを想ったかもしれない。いい気持ちになって想う事は、頬が桜色になるような事だったろう。
母はそれも「捨てなさい」と言う。しかし玉枝にとってそれは昼寝用にはもって来いの物だった。だから、「嫌だ」と答える。捨てなさい、嫌だ、捨てなさい、嫌だ。右左に別れて綱引き合戦をしているようだった。(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|
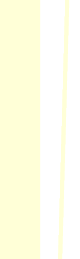 |
 |
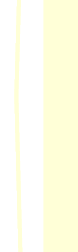 |
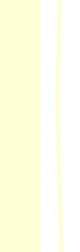 |
 |
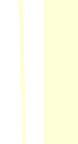 |
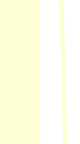 |
 |
 |
 |
 |
 |
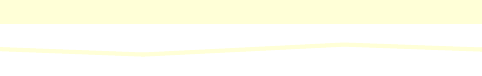 |
 |
