 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
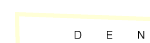 |
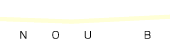 |
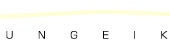 |
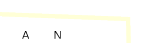 |
 |
 |
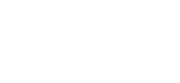 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
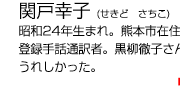 |
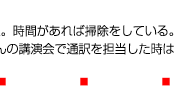 |
 |
 |
 |
 |
 |
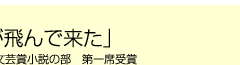 |
 |
 |
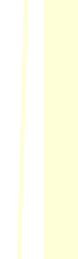 |
ドタン、下から音がした。
時計はいつもの調子で時を刻んでいるからこの分では夕方迄にはまだ時間が掛かりそうだからと、ニ階でうとうとしていた玉枝は目が覚めた。
が、即座に物騒な血の臭いをはらんだ音ではないと直感した。だからかも知れない。一瞬目は勢いよく開いたのだが、またとろりとした空ろな目に引き戻された。しかし音の正体は何なのか、仮りとは言え住人として確かめなければならない責任感が徐に働き、その目に合わせるように、そろりと階段を下りて行った。
下では母が仏壇に置いた父の遺影を床に投げ、微笑んだ父とは対照的な恐い顔をして立っていた。
二度目の出来事だった。
写真立ての枠組みが前よりもっと歪んでしまったが、元に戻しながら今日もまた
「ビール飲もうか」
と、取り乱していない、例えば食事の仕度が出来た時、「ご飯よ」と言う風に気取りのない日常的な声を母に掛けた。
玉枝は一人暮しの母の所へ、ほんの三十日程前に転がり込んでいた。
夫から別れて欲しいと頼まれた。
玉枝は頼まれたら断われない性格だけど、この問題は格が違う。
付き合っていた女性との間に子供が出来たので、その女性と生まれてくる子供を籍に入れたいから、玉枝に出て行ってくれなかと言う。
うろたえた。殺虫剤をスプレーで吹き掛けられたようだった。
「消えるの、私が?」
毒が回って死んだ幽霊のような声で聞いたが返事は帰って来なかった。
日頃からお喋りな夫が無言でいる事は珍しく、めったにない静けさの中で、めったに使わない「セイテンノヘキレキ」と言う言葉が浮かんだ。今、正にそれだ。しかし「ヘキレキ」の漢字が分からない。どうしてこんな時にと思うのだが、思ってしまったのだ。焦った。でも出て来ない。ここですんなり書けたら、「ほらね」と心の中で胸を張り、ほんの一瞬でも夫に勝てたと思えるのに。
漢字が書けない事と、夫への怒りが二重に重なり、重さを支え切れなくなったので、夫の頭を片手で叩いた。手が痛い。夫は叩かれた衝撃から頬や額に垂れた自分の髪の毛を直そうともせず、吐いた事を後悔しているのかホッとしているのか区別のつかない、愚図愚図した態度を見せていた。
そんな夫をつり上がったままの目で見ながら、痛い方の手を猫が傷口を嘗めるように、丁寧に摩った。(つづく)
| バックナンバー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|
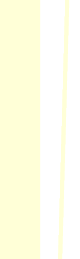 |
 |
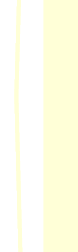 |
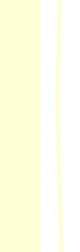 |
 |
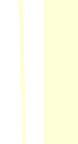 |
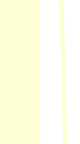 |
 |
 |
 |
 |
 |
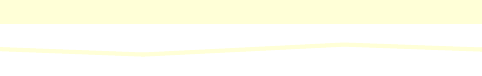 |
 |
