 |
 |
| Vol.49 ある碑(余話)[2009.8.10] |
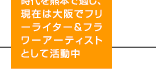 |
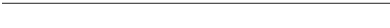 |

|
マイケル・ジャクソンが亡くなって1カ月余り。私にとっては単なる世界的有名人の一人に過ぎなかった人なのに、なぜか、死後しばらくは、猛烈に興味の対象になってしまいました。
サビの部分しか知らないヒット曲の数々、ほとんど記憶に残っていないジャクソン5時代、次第に変わっていった顔や肌の色など、マイケルのことが「もっと知りたい」対象になったわけです。ネットをググり、泳ぎ、週刊誌をあさり、めくり、仕事の合間は“マイケルタイム”。世界を魅了し、また、騒がせもした人ですから、絶賛の声から怪しげなネタまで情報には事欠きません。
それらの中から、私に見えてきた、私が感じた、マイケルです。
| |
■
|
CONTENTS |
| |
(1)
|
バブリーなマイケル |
| |
(2)
|
セクシーなマイケル |
| |
(3)
|
太宰チックなマイケル |
| |
(4)
|
ボーダレスなマイケル |
| |
(5)
|
神になりたかったの? マイケル |
| |
(6)
|
マドンナとマイケル |
| |
(7)
|
ロンリー&オンリーなマイケル |
(1) バブリーなマイケル
特にマイケルの死後に発せられた記事・情報は、「ポップの帝王」として成した偉業に対する好意的なものが大半ですが、中には手厳しい批判もありました。
例えば、「マイケル・ジャクソンの音楽って、どこがいいんだかサッパリ分からない。ジャクソン5やジャクソンズの時のファンクやダンスミュージックなら、普通にその良さが分かるんだけど、ソロになってからの『フー!』とか『ホー!』とか叫んでる『スリラー』とかの一連の楽曲って、ファンの人たちには申し訳ないけど、あたしには、大ゲサな歌謡曲にしか聴こえない。PVのダンスも、別に突出して上手だとも思えないし、あたしにとっては、『自分の容姿に異常なほどのコンプレックスを持った大金持ち』ってだけの存在だった」。
これは、ネットの世界で良くも悪くも有名な「きっこの日記」「きっこのブログ」のきっこさん。相変わらず毒舌容赦なしです。きっこさんは、過去の日記の記述内容からすると洋楽にはかなり詳しいようなので、音楽通の中にはそういう見方をしている人がいるかもしれません。
また、Newsweek日本版で目にした、セス・コルター・ウォルズという記者の記事「僕がマイケルを聴かなかった理由」では、「マイケルは自身の名声によって身を滅ぼすだろうと誰もが確信していた」とシビアです。マイケル全盛期の80年代に少年時代を送った記者らしいのですが、その世代は「マイケルの才能は手放しで褒めたたえても、『マイケルの時代』には違和感を持っている」とのこと。「マイケル自身の成功と転落の引き金を引いたのも、あの時代に花開いた軽薄なゴシップ文化だった」と、浅はかな80年代文化の象徴としてマイケルをとらえています。
つまり、これらの否定的な意見は、「マイケルはバブリーな存在だった」ということに帰するのでしょうか(80年代後半、日本はバブル時代。世界的にも似たような状況があったのでしょう)。
バブルの消費享楽文化は、経済至上主義や量的拡大追求といったイメージと重なるのですが、マイケル急死のひと月近く前に米国自動車GMが、さらにそのひと月ほど前にはクライスラーが、経営破綻しています。大衆消費社会の原形を築き、世界を圧倒したアメリカの大企業の凋落が、彼の訃報に先立って世界的ニュースになっていたことを考え合わせると、感慨深いものがあります。
(2) セクシーなマイケル
さて、こうした“通”の批判は批判として、“素人”の私にとって、ほとんど初めて知ったマイケルの音楽・映像は大変素晴らしく、すっかり魅了されました。
ジャクソン5時代のマイケルの声は、とても透き通っていて深みもあって美しい。14歳のソロ初のバラード「Ben」なんて、まだ子供の愛くるしさも残り、はにかみ気味に歌う姿と伸びのある声がまるごとぐっと心に来ます。そして、次々とヒットを飛ばした全盛期の80年代なんて、カッコいい!! としか言いようがないではありませんか。
キラッと光る目が印象的で、とてもセクシー。いろんな意味で対比される同年の黒人ミュージシャン、プリンス(なぜか私は、彼の「Purple
Rain」はかなり印象に残っています)は、生々しいセクシャルというか、いわゆる「エロさ」が際立っていましたが、マイケルは憎めない「ワル」のようで、ある種、健康的な男の子の性的魅力を発散しているように思えました(後述するように、マイケルは初めから性的魅力を売りにしない黒人だったそうですが、私にはとてもセクシーに映ります)。
ダンスだって、お見事と言うしかありません。ああいうスピーディで精巧なダンスを「キレがある」と言うのでしょうか、激しくも流麗です。見飽きません。スタイリッシュな映像で定評の映画監督、マーティン・スコセッシ(マイケルのPV「Bad」は彼が監督)は、「ステップの一つひとつが完璧な正確さと滑らかさを備えていた。水銀の動きのようだった」と追悼の言葉を寄せています。
有名なムーンウォーク、ロボットダンス、「Smooth Criminal」の前傾45℃傾斜トリック、つま先立ちなどはともかく、私には総体的に、人間のさまざまな何気ない動作をダンスとして昇華する試みを続けていたように思え、そこにマイケルの天性の才能とあくなき鍛錬を感じるのです。な〜んて、素人の感想ですが。
いえ、ニューヨーク・タイムズのダンス批評担当者だって「動きを純粋に動きとして生かした…巨匠」(88年)と評したそうですよ。そして、往年のハリウッドミュージカル映画の名俳優にして名ダンサー、あのフレッド・アステアまでも、マイケルのダンスに舌を巻き、わざわざ電話をかけて讃辞を送ったそうです。
(3) 太宰チックなマイケル
そんなマイケルが、次第に変わっていきます。30歳を迎えた88年ごろには、すでに整形手術で顔は別人のようになり、肌の色も白くなり(人為的に白くしたと噂されていますが、マイケル本人は尋常性白斑という病気によると言っています)、さらには、奇行も目立ってきます。そして、セレブのスキャンダルを追うメディアの絶好の餌食となるとともに、ますます彼のそうした「外見」や「行動」の“変さ加減”がエスカレートしていくのです。
個人的にも親しかった音楽評論家の湯川れい子さんによると、初来日した13歳の彼は「ステージパパに付き添われ、本当に可愛い男子だった」のですが、ロスで再開した21歳の時には、すでに「コンプレックスや人種差別に対する反発心が生まれてきたようだった」とのこと。特に黒人の象徴のようなだんご鼻が嫌で、次第に細く高くとんがって子犬の鼻のようになるわけです。そして、縮れ毛はストレートヘアに、厚い唇は薄くなっていったのです。
また、88年には広大な自宅兼遊園地「ネバーランド」をつくり、「僕はピーターパン」と公言。幼いころからショービジネスの世界で生きて来て、普通の少年時代を過ごすことができなかったがゆえに、その失った時代を取り戻したかったのではないか、と言われています。そして、ネバーランドに子どもたちを招く行動が、少年に対する性的虐待疑惑問題へと発展していくわけです。
マイケルが初めてステージに上がったのは5歳の時。いつも家で歌の練習をし、野球をしたいと思ったこともなく、ステージに上がればみんながお金を投げ込んでくれたそうです。ズボンのポケットは小銭で膨らんでパンパン。ずり落ちるので、いつもベルトをきつく締めていたといいます。リズムに乗って歌うのが楽しくてたまらなく、そして、キャンディがいっぱい食べられるのが本当にうれしかったのだそうです。
そんな彼は、「認めるのは嫌だけど」と言いつつ、「普通の人といると落ち着かない。僕の人生はずっとステージの上だった。普通の人に対して持っているイメージは、喝采と声援と追っかけくらいだ。人混みにいると不安になる。でもステージでは安心だ。できればステージで眠りたいくらいだ」と言っていたそうです。
ヴェルレエヌの詩「選ばれてあることの 恍惚と不安と 二つわれにあり」は、太宰治が『晩年』で引用し、太宰文学の原点にある彼の資質を表す言葉として有名ですが、自分の才能への自負と、対外的な不安に苦しむ傾向は、普通の人でも自我が不安定な青年期によくあることです。だから、太宰文学への傾倒は“青春時代の麻疹(はしか)”とも言われるのです。
マイケルの場合、まさに普通の人ではなく、単なる才能の人でもなく、「神に選ばれた特別な存在」だったとも言えるので、その矜持と苦悩は破格のものであり、また、生涯絶えることのないものだったのでしょう。
ブロードキャスターのピーター・バラカンさんは「気がついたら芸能界の中で、子供らしい幼少期を過ごすことができず、普通の感覚を持てなかったのではないか。『スリラー』が売れすぎたために、それが一つの呪いみたいになった。とても気の毒な人だったと思う」と話しています。
(4) ボーダレスなマイケル
「黒人としてのアイデンティティにこだわってほしかった」というファンは多いようです。が、マイケルは黒人を捨てることにこだわりました。そして、大人になり切れないゆえの女性恐怖もあったのでしょうか(死後、アメリカで「マイケルは小児性愛者と言われていたが、実際には女装を楽しむ同性愛者だった」などと暴露ネタが盛り込まれた伝記が出版され、波紋を呼んでいるそうですが)、「テレビ大菩薩峠」というブログに次のような発言を見つけました。
「(マイケルの)繊細な人格が黒人差別に耐えられず、女性恐怖と相まってネガティブな方向に突き進んだ象徴があの容姿だとしたら、これはマイケル一人の問題ではなく社会的悲劇です。古今東西の成功者は金と女をモルヒネ代わりにコンプレックスなど忘れてしまうものですが、マイケルは『黒人』であることを誰よりも切実に意識していました。私がプリンスよりマイケルの方が好きなのもその部分だと思います」
Newsweek日本版によると、特にマイケルがデビューし、上りつめる時代ごろは、黒人スターは、性的存在としての男を感じさせないことが白人ファンに受ける秘訣でした。なぜなら、白人男性は黒人男性に性的な劣等感を抱きがちだから(黒人のほうが、セックスアピールがあるということですね)。マイケルは、ショウビジネスの世界に長く住んでいてそのことを熟知し(商才とも言えるでしょうし、その世界しか生きる術はなかった者の本能かも)、黒人であることにコンプレックスを覚え、憎悪し、白人化していったということなのでしょう。
そのあたりは、父親との確執も関係しているようです。厳しいステージパパの父親から精神的にも肉体的にも虐待を受けたとか、父親はマイケルを「デカ鼻」と呼んでバカにしたなどと言われています。そして、年を重ねるにつれ、マイケルは自分の顔がその憎むべき父親に似てくるのが許せなかったそうですから。皮肉ですね。父親あってこそマイケルの才能は開花し、偉業を成し遂げたのに、その父親が生涯のトラウマになったのだとしたら。
捨てたのは黒人だけはありません。男であることすらも感じさせないような中性的な姿と雰囲気をまとい、さらには大人になることもを止めて永遠の子どもに、あるいは、成長し老化することをも拒否していこうとしていたのかもしれません。となると、社会的悲劇もさることながら、やはり、彼特有の美意識や価値観、自己不全感などといったものに起因する自ら招いた悲劇の部分が多いようです。
莫大なお金を使い、身体に無理な改造を重ね、「人種・性別・年齢を超える存在」を体現していこうとしたように思えます。
(5) 神になりたかったの? マイケル
80年代の全盛期、マイケル個人のヒット曲とは別に有名なものとして、ライオネル・リッチーとの共作による「We
are the world」(85年、エチオピア難民救済チャリティーを目的としたUSA for AFRICAに参加して制作)があります。趣旨は立派ながら、アメリカ人の自己満足的な臭いもして賛否両論だったそうですが、いずれにせよメロディや歌詞の素晴らしさは、誰しも共感するところです。
こうしたメッセージ性の強い楽曲が、その後、増えていきます。人種差別、戦争、環境破壊、飢餓など、人類と地球の問題をテーマにした楽曲です。「Black
or White」(91年)「Heal The World」(92年)「Earth Song」(94年)などですが、これらは私が今回初めて知ったマイケルの楽曲であり、今まで知らなかったマイケルの一面です(この手の楽曲は、まだほかにもいろいろあるでしょうが)。
「Black or White」では「黒人か白人かなんて問題じゃないよ」と少しイライラ叫び、「Heal
The World」では「(君の心の中にある愛によって)世界を癒そう 素晴らしい場所にしよう」と優しく語りかけ、そして、「Earth
Song」では、今なお戦争や環境破壊を続ける人類に対し、「地球が傷つけられて、血を流しているのがどうしてわからないのか」「生まれ来る子供たちは、どうなるんだ。幸せは、人類は、一体、どうなるんだ」と怒りと嘆きをぶつけています。
「愛によって世界を変えたかったんだ」――そうマイケルは言っているように思えます。興味本位のメディアの餌食になり、巨万の富を目当てに悪意の人々が近寄り、世界が称賛ではなくバッシングや揶揄や危害を加速させつつある中で、なおさら、マイケルの優しくデリケートな心は、純粋にそう願っていたのかもしれません。
しかし、もし本当に人種・性別・年齢を超えて、それを実現しようとしたのなら、それは「神」になろうとしたことにほかなりません。これからの新しい世界を創造する、あるいは、本来の美しい地球に戻す、聖なる救世主。それがマイケルの目指したものなのでしょうか。
特に「Earth Song」のPVは、マイケルの怒り嘆く力によって、荒れた地球の大地や森の映像が巻き戻しされて蘇るという、まさにそんな展開を見せます。そのへんがどうもヒロイズムというか、ナルシストというか(変わっていく自分の容姿は、もうコンプレックスではなく自己陶酔の源泉になっていたでしょう)、私にはなんだか大仰すぎる映像で、商業主義がまぶされた胡散臭さを感じてしまいます。
しかし、この「Earth Song」は、イギリスにおけるマイケルの最大のヒット曲となり、マイケルのお気に入り曲の一つでもあったそうです。それもあって、50歳からの復活をかけた公演の地が、ロンドンだったのかもしれません。
イギリスと言えば、老いても変わらずにカッコよくてセクシーなロッカー、ミック・ジャガーを思い出すのですが、マイケルはミック・ジャガーのように自然体で年を重ね、そのままに輝くことはできませんでした。
そしてまた、復活ということでは、マイケル同様80年代に絶頂期を迎え、セックスシンボルNO.1の男優ともてはやされたミッキー・ロークを思い出します。彼はその後の波瀾万丈の人生により名声も美しいルックスも失ってしまいましたが、その無様さ、生き様を武器に、先頃日本公開された名画「レスラー」(ベネチア国際映画祭金獅子賞・ゴールデングローブ賞主演男優賞)で、見事な復活を遂げています。
マイケルの場合は、多分、ミッキー・ローク以上にスキャンダルに見舞われ、好奇心をそそるだけのゴシップネタで話題にされ、より不幸な状況があったのでしょうが、ミッキー・ロークが「レスラー」に意気込んだように、マイケルにとってロンドン公演は再び栄光を手にする大きなチャンスとして期待していたはずです。しかし、マイケルは、復活できませんでした。リハーサルでは10年のブランクを感じさせない見事なパフォーマンスを見せていたそうですが、成功させねばならないという重圧に必死で耐えていたのでは…そんなお節介な憶測も湧いてきます。
神になろうとしたマイケル(ごめんね、決めつけちゃって)の死は、人間が受け入れざるを得ない“with
nature”“with aging”を拒否したゆえの結末なのかもしれません。
(6) マドンナとマイケル
マイケル同様アメリカ人のスーパースター、マドンナは、奇しくもマイケルと同じ年です。私にとっては、マドンナも世界的有名人の一人に過ぎず、彼女について詳しいことは知りませんが、「強く美しい女」と評され続けていることは知っています。また、マドンナは自力で心身を鍛え、磨き、マイケルは整形や薬物などの他力で体を改造し、心を整備していると言えそうなことを。そして、マイケルがゴシップなどに結局は押しつぶされた観があるのに対し、マドンナはそれを逞しくはねのけてきたということを。
私のこのコラムの前回をお読みの方の中には、私が今回のコラムタイトルを「ある碑(余話)」とした理由にお気づきかもしれません。そう、強引な論ですが、そんなマドンナに生命の基本形であるメス(XX)を、そして、マイケルにメスから派生した生命であるオス(XY)特有の、か弱く繊細なY染色体を感じるからです≪笑≫。
マイケルを知る人たちは、「本当にマイケルは優しかった」と口を揃えて言っています。イージーなレッテルを貼りになりますが、「肉食女子・マドンナVS草食男子・マイケル」という対比も感じます。
で、それはともかく、ネットでも週刊誌でも取り上げていましたが、マイケルとマドンナが取り合っていた一人の日本人ダンサーがいたことをご存じでしょうか。Kento
Moriです。そんな日本人がいたこと自体、驚きですが、そこは割愛し、ネットの「ガジェット通信」の記事を要約すると、こうです。
Kento Moriは、マイケルのダンスに影響されてダンサーになり渡米。結局、マイケルの活動期に間に合わず、マドンナのツアーダンサーの地位を勝ち得ました。しかし、マイケルが、幻に終わった今回のロンドン公演のオーディションを行うことを知り、マドンナとの契約金返上を覚悟でオーディションにチャレンジ。見事、バックダンサーの権利をゲットしたのです。それもマイケル本人により、他のダンサーよりいち早い抜擢だったそうです。
結局、マイケルとマドンナが本人同士で交渉した結果、マイケルのたっての願いも甲斐なくマドンナはKento
Moriを手放しませんでした。そこへ、突然のマイケルの訃報。マドンナは、ツアー直前に急遽プログラムを変更し、マイケルとマイケルを夢見て生きてきたKento
Moriのためにスペシャルプログラムを組んだのです。
そのプログラムとは、いわば“マイケルの再現”。Kento Moriがマイケルの扮装をし、マイケルの名曲に合わせてソロダンスを踊るというものです。そして、その動画を彼女の公式サイトのトップページにしばらくの間掲載したのです(7月までオンエアしていました)。
ガジェット通信の記者は、「マドンナの男前っぷりと優しさにも感嘆するところだ」と述べていますが、私は、二人はいわゆる
“戦友”だったのだと思います。才能に恵まれ、富と名声を得た二人。人々の支持を受け続けるために自分の可能性と闘い、そして、富と名声を得たが故に好奇や悪意を向ける社会と闘わなくてはならない、そんな希代のスーパースター同士だったのですから。
そしてまた、種の保存のために悠久の自然・時間と闘う戦友としてのXX染色体とXY染色体の共闘戦線を、マドンナとマイケルのこの話に見て、うれしく思うのです≪懲りずに、笑≫。
「涙が止まらない。世界は偉大な人物を失った。でも、彼の音楽は永久に生き続ける」――マドンナの追悼の言葉です。
(7) ロンリー&オンリーなマイケル
冒頭で触れたNewsweekのセス・コルター・ウォルズさんですが、彼は、もし自分が「マイケルの魂を理解したいと思ったら」ある映画を見るだろうと言っています。ハーモニー・コリン監督の実験的映画「ミスター・ロンリー」。この映画こそ「おそらくマイケルの人生を最も詩的に表現した芸術作品だろう」とのことです。
私の知らない映画(日本では昨年2008年2月に公開)ですが、主人公はマイケルの「そっくりさん」を生業とする男。その物まね屋さんが、マリリン・モンローのそっくりさんと出会い、二人同様さまざまなスターの物まねアーティストとして生きる人々が集まり、共同生活を送る島に行く。そして、マイケルのそっくりさんはマリリン・モンローのそっくりさんに恋をし、心に傷を抱えた者同士が、しばし癒されるひとときを持つ……もっと深い意味のある映画のようですが、大体はそんなところです。
登場するのはあくまで「偽マイケル」などであり、決して本人たちのことを描いているわけではないようですが、セス・コルター・ウォルズさんは「この映画が詩的なのは、魂の平安を得られずに破滅的な人生を送った本物の大スターたちも、つかの間安らぎを手にいれたように見えることだ」と。つまり、本物のマイケルもマリリン・モンローも、生涯安らぎを得ることはなかったということですね。
だからといって、マイケルは孤独だったと、私がわかったような顔をして同情しているわけではありません。コラムニストの小田嶋隆さんは言っています。「マイケルが幸福だったかどうかという質問は、愚問だ。マイケルのようなスーパースターは、幸福とか不幸といった、俗世間の指標の届かない、はるか彼方に住んでいる。別の見方もある。幸福は、多数派の特権だ。多くの人々はそう考えている」と。けだし名言です。
作家の村上春樹さんは「僕の作品は誤読の集合」と言っているそうですが、マイケル・ジャクソンという人ほど「誤解の集合」はないかもしれませんね。そして、彼のことを知りたいと情緒を揺さぶられた私も、遠くから彼を眺め、自分なりに彼を感じ、その集合の一部をこうして綴ったわけです。マイケルは、誰もがそうであるように「本人だけしか知らない一回限りの存在」を終えたんだ、と嘆息めいたものを覚える私。まさに“もののあわれ”なり、ということでしょうか。
|
 |
| |
 |
|